一日三語。シンプルイズベスト?
かつて、昭和の亭主関白な家庭内の会話は
「風呂・めし・寝る」
だけで済むという笑い話がありました。
私は『サザエさん』で、ノリスケからその話を聞いたマスオがサザエ相手に通用した話を見た記憶があります。

でも、全く会話にならないですよね。熟年離婚にならなきゃいいけど
こんなもの、時代錯誤も甚だしいと思うかもしれないですが、実は現代でも同じようなことをしている人は意外に多かったりします。
伝わらなければ意味がない
私の本業の顧客の大部分は、理工系の学生や大学教官、メーカーや研究機関のエンジニアや研究者です。
仕事をするには一定レベルの工学的素養が前提となります。
たとえ同じ業界人同士であっても、結局コミュニケーションは人対人なので、自分が望む結果を相手に求めるには、まず自分の話す・書く内容が相手に伝わるようにしなくてはなりません。
コミュニケーションの最大の狙いは「伝えること」ではなく「伝わること」です。
私も他人のことは言えないのですが、これが大学まで行っても結構できていないものなのです。
平成初期の新人時代、いつも質問を二言三言で送ってくる某大学教授がいました。
例えばこんな感じ:
– ポンチ絵のfax送信
-メール(「さっさとFaxを見ろ」をにおわす数行のメッセージ、傍から見ればイミフ)

・・・
昭和時代、新聞の下方の広告欄では、家出や絶縁したとみられる親兄弟や親戚縁者に連絡を呼びかける「たずね人」関連の短いメッセージが頻繁に見られたものですが、思わずアレを想像しちゃいましたよ。
もちろん、販売したソフトウエアで対応できることは限定されていますから、これだけでも何を求めているのか全くわからないことはありません。
ですが、モノクロの、決して上手いと言い難い(=へったくそな)絵と解読困難な手書きの数式だけで、私がいつも質問内容に沿う回答ができるとは限りません。
いや、できないケースの方が圧倒的に多かったのです。
できなければ、何回も電話なりメールなりで内容確認を繰り返すことになり、余計な時間がかかります。
その間、先生のイライラは募り、私もウンザリ。
いうまでもなく、こんなのはWin-WinならぬLose-Loseです。

登場人物全員が不幸・・・
ここで問題なのは、回答に要する時間ではなく、その前段階の質問内容の解釈に要する時間。伝わっていないのが原因です。
前者は回答する側の努力(私の責任)で短縮可能(要するに私の責任)ですが、後者は質問する側の努力(先生の責任)がないと短縮できません。
努力といっても、面倒くさがらずに第三者でも質問内容が的確に読み取れるように書くだけです。
論文を書くわけじゃあるまいし、思っているほど手間暇がかかることはありません。
何といっても、自分の質問内容は自分が一番詳しいのですから、自分が望む結果を効率よく得るために自分でコントロールできる余地は大きいのです。
相手の理解が前提?
過去30年以上のネット技術の進展でコミュニケーションツールの多様化が進みました。
現代は動画が主流ですが、やはり基本は文章です。
近年は発信側の動画はショート、文章も短い、文字数の少ないものが多くなっています。
これは受信側として短時間でわかりやすいものが好まれているためですね。
世代を問いませんが、特に若年世代は長文を敬遠する傾向があります。
研究によれば、言語能力は読書速度の核心で、大量の本を読むことで長い文章が読めるようになるそうです。
メディアの調査では彼らは本を読まなくなっていますが、これは長文を読まないことの必然の結果といえます。
であるので、文字数の少ないSNSが日常的なコミュニケーションツールになっているのも自然な成り行きといってよいでしょう。
このような短文メッセージでコミュニケーションが取れるためにはある条件が必要になります。
それは「相手が理解(認知)してくれる」こと。
たとえば、相手が友人知人とか家族であれば、自分に関する一定レベルの情報を共有していますよね。
相手が理解してくれるからこそ、ある程度知っていることを前提とした短文メッセージのやり取りでコミュニケーションが成立するのです。
しかし、相手の理解が前提ということは相手に依存してしまうということなのです。
はたしてそれでよいのでしょうか。

視野が狭くなりそう
AIの時代だからこそ
有名な『7つの習慣』には私的成功のための3原則があります。
その第一歩が主体性を発揮することであって、他者の評価や社会通念に依存せず、主体的に考え行
動するものとされています。
私的成功は良好な人間関係の構築を土台にしています。
主体性のない、相手に依存するようなコミュニケーションは、交友範囲を狭め偏ったものにしてしまいます。
自分をコントロールする力を放棄してしまっているのでは、自己変革や成長のチャンスを逃しかねず、私的成功から遠ざかってしまうのです。

勿体ないですよね
冒頭の「風呂・めし・寝る」のコミュニケーションは、相手に昭和の価値観の理解があれば成立するものです。
繰り返しますが、時代錯誤だし、高齢者の甘えだとも思います。
しかし、ただの世代間ギャップではなく、今でも世代にかかわらず数々の場面で無意識にとっている相手に依存したコミュニケーションも、形は違えど大して変わらないのです。
一昨年から生成AIを使ったデジタルコンテンツ作成が爆発的な勢いで増えていますね。
しかし、現在の技術レベルでは生成AIは人間からの適切な指示(プロンプト)がないと機能しません。
ここでも指示内容がAIに的確に伝わることがキーになっているのです。
AIを使いこなすのが当たり前の時代の今こそ、「風呂・めし・寝る」の貧しいコミュニケーションから決別する一大チャンスだと思います。
コミュニケーションではシンプルは必ずしもベストではないのです。
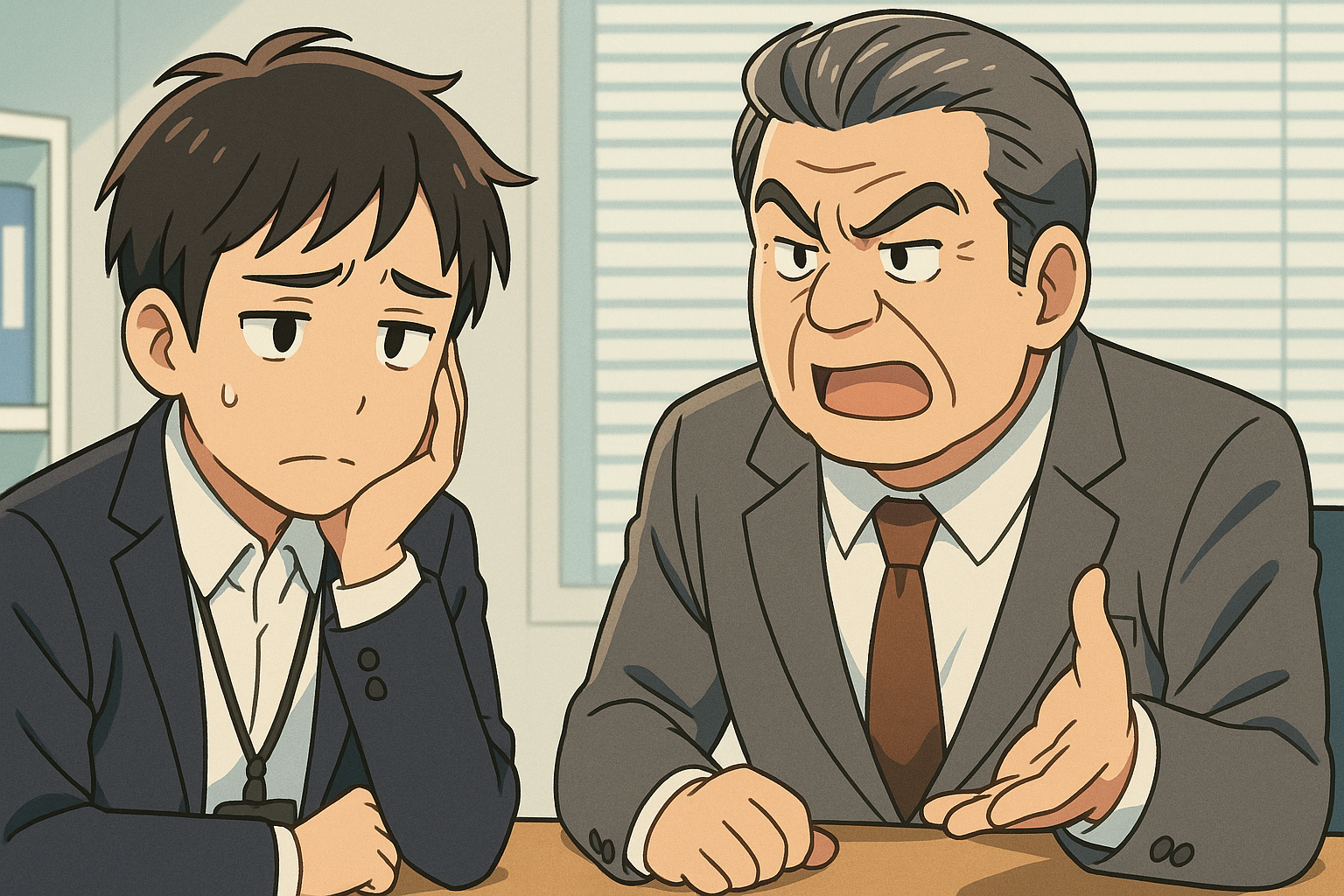

コメント